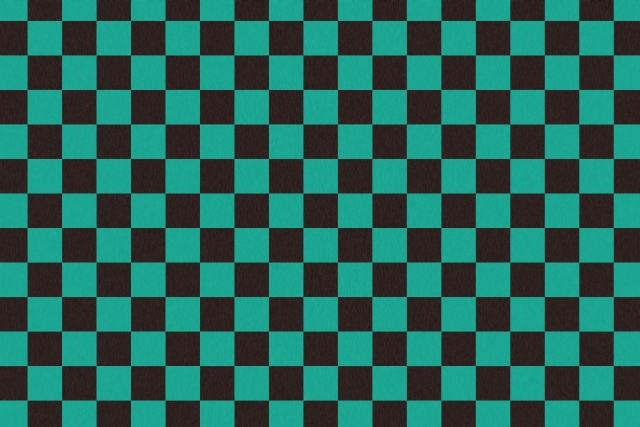【考察】千寿郎くんはなぜ自分の日輪刀を持っているのに「隊士」ではないのか
単行本第8巻で千寿郎くんが「僕の日輪刀は色が変わらなかった」と言うシーンを見て、「あれ?」と思いませんでした?
日輪刀って、普通は”最終選別”を突破した後に、鬼殺隊から支給される刀なんですよ。もしかして千寿郎くんは”最終選別”を突破してるんでしょうか?
”最終選別”は突破している可能性あり
結論としては、「”最終選別”に合格して日輪刀を支給されたけど、色が変わらなかった」と考えます。
ただし千寿郎くんが”最終選別”に行ったという描写は2021年5月現在、公式のどこにもありません。また隊服を着た描写もありません。
鎹鴉に関しては、炭治郎に手紙を出したり文通したりしてるので、自分のとは限りませんが使えるようです。
最終選別を突破したと考える根拠
「最終選別を突破した」と考える根拠は以下のセリフです。
「本当なら私が継子となり」「柱の控えとして実績を積まねばならなかった」
『鬼滅の刃』第8巻p157より
という部分。
まだ”最終選別”に合格していないなら、「継子」「控え」「実績」というワードの前に、「本当なら僕がはやく隊士になって」というようなセリフが千寿郎くんから出てきませんか?
「継子になれなかった」「柱の控えとして実績を積めなかった」と悩むのは、”「隊士」にはなれたけどそこまでだった”という嘆きではないですか?
日輪刀の色が変わらなくても鬼殺隊に入れる?
不死川玄弥の例
呼吸が使えなくても”最終選別”に合格した例として、不死川玄弥が挙げられます。
「呼吸が使えないと日輪刀の色が変わらない」のかどうかはよく分かりませんが、呼吸が使えなくても鬼殺隊には入れるようです。玄弥は階級も上から4番目の”丁(ひのと)”まで上がっています。
玄弥の日輪刀の色に関しては公式では記載がありませんが、アニメなどでも見た感じ色は変わっていないように見えます。
関連記事→【研究】不死川玄弥(しなずがわげんや)
日輪刀の「色変わり」に必要なもの
「剣術の技量」と「身体能力」?
また千寿郎くんは「ある程度の剣術を身に付けないと日輪刀の色は変わらない」と言っています。
玄弥も「剣術の才はない」と言われているので、「日輪刀の色変わり」は剣術の方と関連性が高いのかもしれません。
”赫刀”を発現させるときも、刀を万力の握力で握りこんだり、刀同士を打ち合わせたりしているので、日輪刀に何かしらの刺激を与えることが必要だと思われます。
「呼吸」が知られていなかった鬼殺隊初期の時代から、日輪刀は「色変わりの刀」と言われていたはずなので、個人がもつ「剣術の技量」「身体能力」が日輪刀に刺激を与え、色が変わると考えられます。
「精神力」も必要?
そして「剣術の技量」「身体能力」が日輪刀にしっかり伝わるためには、「精神力」も重要なのではないかと思います。
いわゆる「心技体」ですよね。これらが揃わないといけないとしたら、千寿郎くんに足りないのは、「心」ではないでしょうか?
もしかしたら、「自分のすすむ道」を自分でしっかりと決めたあとの千寿郎くんは、日輪刀の色が変わったのかも知れません。
色変わりの仕組みをちょっと妄想
人間は掌でも色を感じることが出来ると言われています。
ということは、刀を握ることで日輪刀のなかにある様々な色の特性を感じ取り、刀と身体を一体化させることで色が変わる、というような妄想をしてみました。
千寿郎くんが「隊士」として活動していない理由
”最終選別”に受かっているとして、なぜ千寿郎くんは「隊士」として活動していないのでしょうか?
活動を「休止」または入隊を「保留」されている?
「隊士」になっても、神崎アオイのように実戦に参加しない「隊士」もいます。
千寿郎くんが実戦に行かない考えられる理由としては、
- 日輪刀の色が変わらなかったので、「もう少し追加で稽古しようね」と「保留」された
- 実力が足りないことを知った槇寿郎or杏寿郎が任務の斡旋を止めている
などが考えられます。
「隊士の質の低下」が問題視されている時期でもあった
那田蜘蛛山の戦いの後で行われた柱合会議では、議題として「隊士の質の低下」が挙げられています。
年齢を考えると、千寿郎くんが”最終選別”を受けたとすれば炭治郎よりも少しあとの回だった可能性が高いです。
この頃だとちょうど那田蜘蛛山の戦いの前後ぐらいになるので、千寿郎くんが受けたかもしれない”最終選別”あたりから、「鬼殺隊」の新人隊士に対する方針が変わった可能性があります。
方針が変わってなかったとしても、明らかに実力が足りていないものを無理に入隊させなくても良い状況だったのは確かだと思います。
槇寿郎や杏寿郎の意向が働いている?
槇寿郎さんはもともと、杏寿郎さんにさえ「才能が無い」と言って稽古をつけるのを止めています。
杏寿郎さんはその理由について、「煉獄零話」(公式ファンブック・弐に収録)で「自分たちを死なせたくないからでは?」と想像しています。
たとえ”最終選別”に合格したとしても、「刀の色が変わらない」実力では、すぐに死んでしまうのは目に見えています。
槇寿郎さんも杏寿郎さんも、入隊してすぐに死んでいってしまう隊士たちをたくさん見てきたはずです。千寿郎くんが隊士としては「難しい」と冷静に判断し、活動を「休止」または入隊を「保留」にさせたのではないでしょうか?
そもそも「隊士にさせたくない」と考えていたのかもしれません。
それぞれの思い
父や兄の思い
煉獄家は代々”炎柱”を受け継いできた家系で、槇寿郎さんも杏寿郎さんも子供のころから鬼殺の道しか知らずに生きてきたはず。
いつまでも無惨を倒せないことに加えて時代の変化もあり、煉獄家や鬼殺隊の在り方に、槇寿郎さんや杏寿郎さんは疑問を持っていたのではないでしょうか。
そして、千寿郎くんに違う道を選ぶ機会と時間を与えたかったのかもしれません。
千寿郎くんの思い
千寿郎くんは毎日稽古はしていたようですが、実力はなかなかあがりませんでした。
オリジナルCD(これは時系列と内容で悩む部分がありますが)では、「一年ぶりに杏寿郎が稽古をつけた」とあります。もしかして杏寿郎さんのときと同じく、正しく指導する人がいなかっただけの可能性もあります。
槇寿郎さんは稽古をつけることはないですし、杏寿郎さんも積極的に稽古をつけることはしていなかったのかもしれません。
学校に行ったり、家事全般までやっていたとしたら、自分だけで修行するというのはかなり難しいものがありますよね。
幼い頃に剣術の手ほどきをしっかりと父親から受けた杏寿郎さんよりも、修行の条件が悪かったのはたしかです。性格的にもおとなしく、自信を持って修行や鬼殺にのぞむタイプではなさそうです。
ただ現代編では、産屋敷家の神社で「炎の呼吸」の神楽も奉納されているようなので、「炎の型」はその後きちんと継承されたと見られます。
「剣士」以外で働くという選択もあるのでは?
杏寿郎さんはオリジナルCD『煉獄杏寿郎の使命』で千寿郎くんに、「視野を狭くしてはいけない」「人の役に立てることは剣の道だけか?」と言っています。
また本編では「自分の心のまま正しいと思う道を進め」と千寿郎くんに伝えています。
しかし「剣士」以外、たとえば「隠」などで働くことは、ずっと「剣士」を目指してきた千寿郎くんには時間のかかる選択だと思います。「もっと剣術稽古を重ねよう」と、まだまだ若い千寿郎くんはまず考えるでしょう。
”最終選別”前に日輪刀を持っているのは不自然
そもそも、隊士でもない少年が事前に色変わり前の日輪刀をもらうのも不自然です。
”最終選別”に受かった後日輪刀をつくるための玉鋼を選びますが、そのときに「僕もう自分の日輪刀持ってるんで」ってなったら、その時点で同期間でも「ザワザワ」ってなりますよね。同期間の連帯に悪影響を及ぼしそうです。
日輪刀は材料から考えても貴重なものっぽいですし、刀一本をつくるのにも手間と時間がかかります(作中では玉鋼選びから納品まで約二週間)。
折ったり曲がったりしても大変ですし、修行中から新品の日輪刀を与えておくメリットは無いように思います。
炭治郎や善逸たちも、修行中のときの刀は普通の日本刀に見えました。
千寿郎くんの年齢は?
千寿郎くんの年齢は、スピンオフ小説『鬼滅の刃・片羽の蝶』第5話で「時透くんと同じ年頃」とあり、炭治郎よりは下に見えるので、8巻時点で12~14歳ぐらいが想定されます。
見た目でいうと、杏寿郎さんが”最終選別”に合格した頃と同じぐらいかもう少し下に見えます。
千寿郎くんが生まれたときや幼い頃の杏寿郎さんの描写をみると、6~7歳差ぐらいに見えます。杏寿郎さんが20歳なので、そこからも13~14歳ぐらいになります。
千寿郎くんの身長は炭治郎よりも低いので、165cm以下は確定です。現代の平均身長で考えても、やはり13歳ぐらいではないでしょうか。
炭治郎は15歳、冨岡義勇は13歳で”最終選別”を通過しています。時透くんなんか、13歳頃にはもう”霞柱”やってたはずですので、年齢的には”最終選別”を通過していてもおかしくないです。
まとめ
以上から、”千寿郎くんは選別を突破したけど日輪刀の色が変わらず、活動を「休止」または入隊を「保留」にしている”のではないかと考えます。
時期的にも「隊士の質が落ちている」と柱合会議で議題になっている前後なので、すぐに隊士にさせる雰囲気でもなかったのかもしれません。また、「弟を死なせたくない」「鬼殺に関わらない道も考えさせたい」という杏寿郎さんの思いも少しはあったように思います。
後になっても千寿郎くんが戦闘に参加した様子はないので、実戦のサポートよりも、もっと後方で出来る「人の役に立てること」を選んだのかも知れません。
実際に”歴代炎柱の書”を修復して、内容を炭治郎に伝えてもいます。
もしかしたら、「自分のすすむ道」を自分でしっかりと決めたあとの千寿郎くんなら、日輪刀の色が変わったのかも知れません。
公式ファンブック・弐によると「炎の呼吸」の神楽は現代でも産屋敷家の神社で奉納されていると思われるので、きちんと継承も出来たようです。
きっと、無惨討伐後の世界では、千寿郎くんは「刀を持たずに人を助ける道」で活躍していることでしょう。