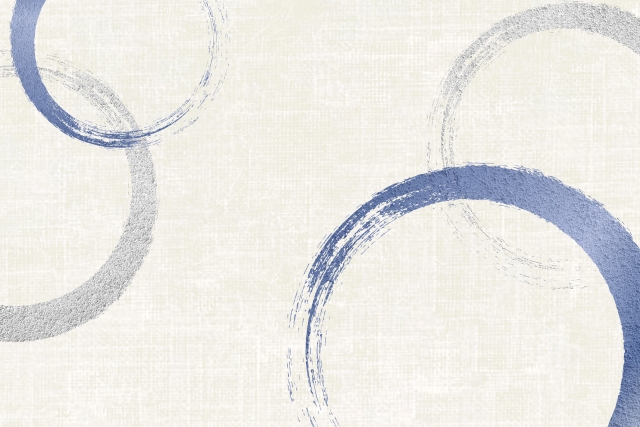【考察】”最終選別”を考える

”鬼殺隊”に入るためには、”藤襲山(ふじかさねやま)”で行われる”最終選別”を突破しなければなりません。
炭治郎たちが合格した回では、20名以上参加して合格者5名と厳しいものでした。
今回はこの”最終選別”を考えてみたいと思います。
以降、最終巻までのネタバレを含みますので、未読の方はご注意ください。
通過するためには
条件は「7日間生き延びること」
「7日間生き延びる」こと。通過条件はこれだけです。いたってシンプル。
どのように行動すべき?
無理にひとりで鬼を倒さなくて良い
生き残ることができればいいので、無理に鬼を倒しに行かなくていいんです。手に余る鬼が居れば逃げてもいいし、仲間と協力して倒してもいいんです。
休息できる場所をきちんと確保する
炭治郎は「7日間生き延びる」ことを最終目標とし、まずは「東を目指す」「夜を越える」ことを最初の目標にしました。
7日間生き延びるためには、休息も必要です。
山の中はうっそうと木が生い茂っているので、昼も日当たりは悪そうです。それでも太陽の光が入りやすい東側に移動することで、きちんと身体を休められる場所を確保しやすくなります。
炭治郎はちゃんと、7日間を乗り切るための計画を練っていたようです。
7日間野宿で体調を維持するための知識が必要
大正時代に「サバイバル」という言葉はないと思いますが、山の中で7日間暮らすというのは、結構ハードです。
飲み水や食料の確保、火を起こしたりも必要です。
7日もあるので、痛んだ水などを飲んで体調をくずしたり、変な虫に刺されたりして治療できなくてもアウトです。「体調管理」が超重要となる7日間なのです。
夏場は夜は短くて楽そうな気がしますが、虫や雨も多く、台風に当たったら最悪です。夏場を狙った志願者が増えても困りますし、もしわたしが責任者なら、夏場は”最終選別”は休止期間にします。
でも食事とかどうしてたんでしょうね?山奥に配給があるから鬼のいる中を移動して取りに来い、みたいな感じでしょうか?
”最終選別”で試されること
無理に鬼を倒さなくても良い、鬼を倒した数が問われないなら、”最終選別”ではいったい何が試されるのでしょうか?
「鬼」のいる山で7日間過ごす精神力があるか
「鬼」のいる山に7日間閉じ込められる、というのは精神的にかなりこたえるはずです。
常に「鬼」が周囲にいる状況で通常の精神状態を保てるかどうか、ということは”鬼殺隊”として大事なポイントです。このあたりをきちんと確認しないといけないですよね。まあパニックになるようならほぼ生きて山を出られないわけですが。
このあたりは修行の段階では判断がつかない部分なので、”最終選別”の肝とも言える部分でしょう。
「鬼」を斬る覚悟があるか
「7日間生き延びる」ことが条件だとしても、確実に「鬼」とは遭遇します。逃げてもいいですが、確実に逃げられるとは限りません。
実際に「人の形をして動いているもの」をためらわずに斬ることは難しいです。でもためらったらきっとやられてしまうでしょう。
そして、斬ったあと本人がどう感じるか。”隊士”になったら、それがずっと続いていくわけですから、覚悟が問われます。
前身作『鬼殺の流』で書かれていたこと
『鬼滅の刃』の前身となった『鬼殺の流』という作品(『鬼殺隊見聞録』に一部収録)では、「最終選別」の7日間で「鬼の気配を察知する能力を身につける」という記述があります。
”最終選別”の疑問点
年に何回”最終選別”を行っているのか
小説版「遊郭編」にて
「年に一回行われる」という記述がされています。
ただ、本当に一回だと、いろいろ矛盾が出てくるんですよね。炭治郎の勘違いか思い込みかも知れません(笑
「年に一回」ではない?
”霞柱”時透くんと”恋柱”甘露寺さん、このふたりは数ヶ月差で”隊士”になったと考えられるので、少なくとも年に1回ではなさそうです。それとも実は覚えていないだけで、神崎アオイとともに三人ともいっしょの選別だったのでしょうか?
年あたりの死者数から計算してみる
1回あたりの合格者が平均3名とした場合で、死者数とのバランスで考えてみます。
那田蜘蛛山では10名以上が死亡、「無限列車」では数名死亡、が確認されています。この年は死者数が多かった年かもしれませんが、年に20名ぐらいは死亡してそうです。
そうすると補充も20名ほど必要なので、平均3名の合格者だと年に6~7回は開催される計算になります。
”隊士”の総数から計算してみる
数百人いると言われる”隊士”たち。
仮に300人としてみましょう。
入隊者全員が15歳で入隊して35歳で引退する場合、活動年数は約20年。同い年の隊士は300/20=15人=一年あたりの入隊者数、になります。
実際は途中で死んでしまう隊士が多いはずなので、やはり毎年最低でも20人は補充しないと人数が維持できないのではないでしょうか?
するとやはり、年に一回の試験では足りないような気がします。
それとも、炭治郎たちが受けた回は特殊で、難易度が高かった、もしくは受験者のレベルが低かった、のでしょうか?
「鬼」はどうやって調達しているのか
かつて鱗滝さんに捕らえられたという鬼もいたので、隊士が「ちょうどいい鬼」を捕獲しているのだと思います。
ですが、”最終選別”1回あたり30~50体の鬼が必要だとしてですよ?無惨様しか「鬼」を増やせないのに、どれだけ無惨様と隊士たちは働いているのでしょう?
年に6回あれば、少なくとも年に200体は調達してこなければなりません。
”藤襲山”以外にも鬼はいるし、一箇所にこれだけ鬼が集められたら無惨様も気がつきそうな気がしますが。
もしかしたら”藤襲山”にいる「鬼」は、無惨様がつくった鬼じゃないのでは?という疑惑もわいてしまいます。
なお、『吾峠呼世晴短編集』に掲載の「過狩り狩り」では、「藤襲山」の鬼は19体となっています。
志願者に対して死者数が多いのでは?
例えば、炭治郎たちが受験した回では、20名以上受験して5名しか合格していません。
不合格の全員が死んでしまったとは限りませんが、せっかく修行して力をつけたのに隊士になれないのは、効率が悪くないですか?
でも、これに関しては、合格して生き残った者に、「生き残った者としての責任」を植え付ける意図があるんじゃないかと思います。
隊士になって鬼を倒そうとしていた仲間の思いを継ぐ、という意識を持たせることで、精神面の強さを保たせる、という目的もあるのではないでしょうか。
まとめ
”最終選別”の合格条件は「7日間生き延びること」。
そのためには無理に鬼を倒そうとせず、太陽を味方にして身体を休め、体調管理にも気を配るなどの「計画的な行動」が求められます。
また”最終選別”で試されることは、たくさんの鬼を斬れる戦闘力ではなく、「鬼のいる場所で通常の精神を保てるか」「鬼を斬る覚悟はあるか」の二点だと考えます。
”最終選別”の時点で強いに越したことはありませんが、もっとも見られるのは「鬼狩りとして過酷な生活が出来る適性があるかどうか」なのではないでしょうか。
そして隊士になって鬼を倒そうとしていた仲間の思いを継ぐ、という意識を持たせることで、精神面の強さを保たせる、という目的もあると考えます。